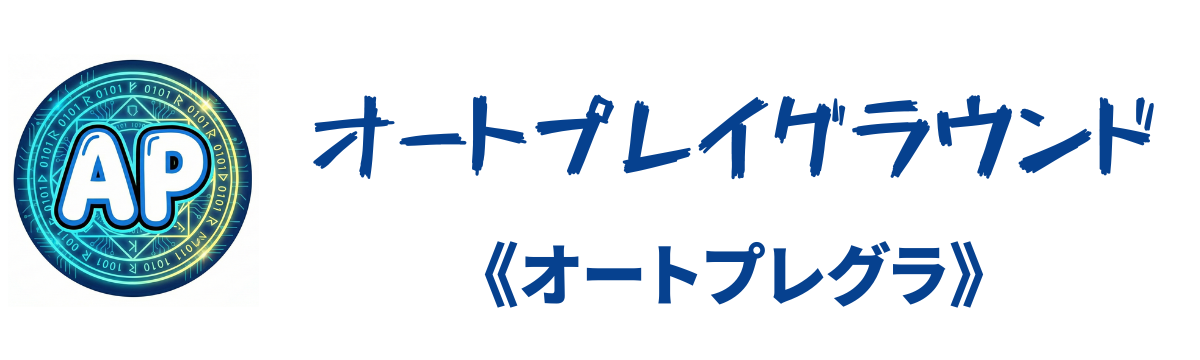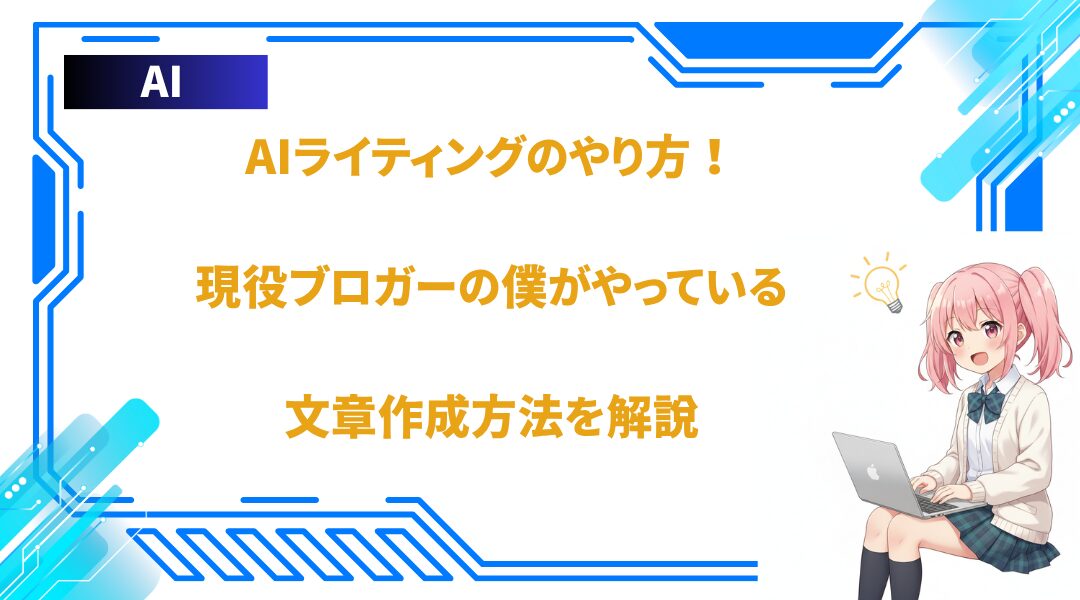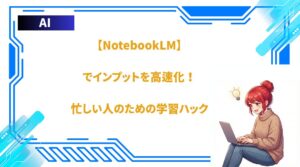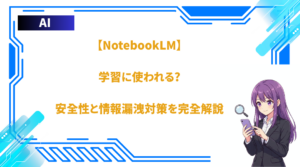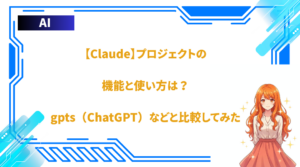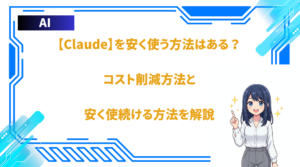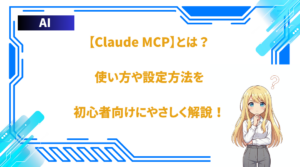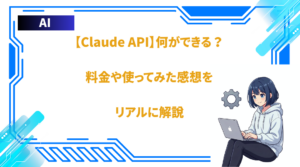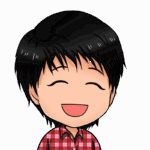 ヨネティ
ヨネティこんにちは!ヨネティ(プロフィール)です!



・AIライティングって最近よく聞くけど、具体的にどうやって始めたらいいの?
・たくさんツールがあるけど、どれが自分に合っていて本当に使えるの?
・AIで書いた記事って、SEO的に大丈夫?本当にブログで稼げるようになるの?
など思っている人もいるのではないでしょうか?
「AIライティングのやり方」って、いざ調べてみても専門用語が多かったり、ツールの紹介ばかりで、実際にどう手を動かせばいいのか分かりにくいですよね?
本当に初心者でも、AIを使いこなして質の高いブログ記事が書けるようになるのか、不安に感じていませんか?
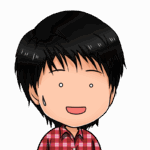
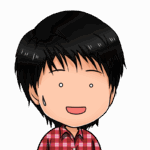
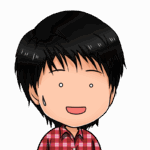
めちゃ分かる…!
僕も最初は手探り状態で、色々なAIライティングツールを試しては「何かか違う…」と挫折しかけた経験があります…!
楽することだけ考えて必死にやってました(笑)
「AIライティング」は、AIを活用して文章を作成する、まさに次世代のライティング手法です。
うまく使えば記事作成のスピードが劇的に上がりますが、ただAIに丸投げするだけだと内容が薄かったりありきたりな文章になったりして、結局使えない…なんてことになりがちなんですよね…
そこで今回はAIライティングのやり方について、「僕が実践している具体的な5ステップ」「代表的なAIツールとその選び方」「AIで稼ぐための注意点とコツ」について徹底解説します。
- 初心者でも迷わない、AIライティングの具体的な手順5ステップ
- あなたの目的に合ったAIライティングツールの選び方と、代表的なツールの特徴
- 「AIライティングは稼げない」という噂の真相と、AIを活用して収益を上げるためのコツ



それでは本題を解説していきます!
この記事はAIライティングのやり方をマスターし、あなたのブログ作成を劇的に効率化する方法を具体的にお伝えしています。 ぜひ参考にしてみてください。
【結論】僕のAIライティングのやり方5ステップ


AIライティングは、実はだれでも簡単にはじめられます。
特別なスキルがなくても、正しい手順をふめば、質の高い記事が作れます。
ここでは、僕が実践しているAIライティングのやり方を5つのステップで紹介します。
- ステップ1:キーワード選定と検索意図とペルソナの設定
- ステップ2:読者を引き込む記事構成の作成
- ステップ3:AIによる本文ドラフトの生成
- ステップ4:独自性を加えるファクトチェック
- ステップ5:SEOを意識した最終リライト
ステップ1:キーワード選定と検索意図とペルソナの設定
AIライティングの成功は、キーワード選定と検索意図やペルソナから始まります。
AIで記事作成しようが自分で記事作成しようが、実はここが一番重要。
特にAIで書く場合はキーワード・検索意図・ペルソナの設定できてなければ、想定していた記事とは全く違う意図の記事ができてしまいます。
例えば、個人向けに書いている記事がよく読んだら企業向けになっていたりします。
修正量も増えかえってライティングに時間がかかったり、意図と違うため離脱されたりするので、必ず設定しましょう。



僕も最初は設定してなくて、AIライティングのほうが時間かかっていました!
ステップ2:読者を引き込む記事構成の作成
次に、読者が最後まで読みたくなるような記事の構成を考えます。
まずはAIにキーワードを伝え、構成案(見出し)のたたき台を作ってもらいましょう。
次に、狙うキーワードで検索し、上位表示サイトの見出しを参考に必要な見出しを作っていきます。



ラッコキーワードで検索し、スプレッドシートやエクセルにまとめるとやりやすいです!
最終的にはAI案と上位サイトを分析し作った見出しに、自分が読者になったつもりで見出しを見直します。
上位表示やAIにない見出しで、自分が欲しいものを追加しましょう。このひと手間が、読者を満足させる記事作りのカギになります。
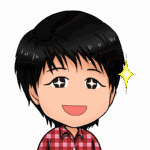
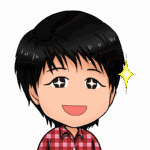
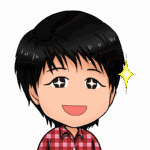
STEP1とSTEP2でAIライティングの90%は決まります!
ステップ3:AIによる本文ドラフトの生成
構成が決まったら、いよいよAIに本文のドラフトを書いてもらいます。
作成した見出しごとに、AIへ文章作成の指示を出していきましょう。
このとき、ペルソナや文のトーンなど、細かい条件を指定するのがコツです。
AIが生成した文章は、あくまで下書きとして使います。
AIは、時間のかかる執筆作業を助けてくれる、強力なアシスタントです。



本当に本文を書くのが劇的に楽になりました!
ステップ4:独自性を加えるファクトチェック
AIが書いた文章は、必ず情報の正しさを確認します。
AIは時々、間違った情報や古い情報を作ってしまうことがあるからです。
信頼できる公式サイトや専門家の情報源で、内容を一つずつチェックします。
同時に、自分の体験談や独自の視点を加えることで、記事に魂を吹き込みます。
このひと手間が、読者からの信頼につながる大切な作業です。



最も重要なのはここです!
STEP1〜3は表面的な部分をサポートしているだけです!
ファクトチェックと独自性を入れることで他のサイトとは違う魅力が現れます!
確かにこの時点でほぼ記事は完成していますが、ここは最も時間をかけるべき作業です!
ステップ5:SEOを意識した最終リライト
最後に、検索エンジンに評価されるように文章を整えます。
キーワードを不自然にならないように含めたり、共起語を入れたりします。
読者が読みやすいように、難しい言葉を簡単な表現に変えることも重要です。
スマホで読まれることを意識して、改行や箇条書きをうまく使いましょう。
最終チェックで、読者にとっても検索エンジンにとっても最適な記事が完成します。



AIだけに任せず自分でも修正することが重要!
AIライティングとは何か?


AIライティングとは、人工知能を使って文章を作成することです。
ブログ記事や広告文など、さまざまな文章を自動で生成できます。
ここでは、AIライティングで何ができるのか、3つのポイントで解説します。
実際に自動で記事ができる?
AIライティングツールは、記事のたたき台を自動で作ってくれます。
しかし、ボタン一つで完璧な記事が完成するわけではありません。
見出し作成や本文執筆など、多くの工程をAIが助けてくれます。
AIが作った文章は、必ず人の手で修正することが大切です。
あくまでAIはアシスタントで、仕上げは人間が行う必要があります。



僕自身も見出し構成や、修正に多くの時間を使っています!
ただし、AIを導入することで劇的にライティングが楽になりました!
どれくらい効率がいいのか?
AIライティングを導入すると、作業効率は飛躍的に向上します。
記事作成にかかる時間が半分以下になりました。
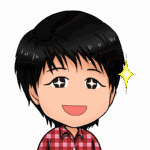
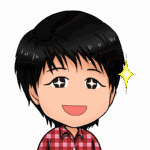
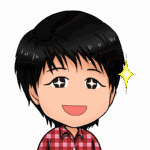
僕の場合1万記事を書こうと思えば一日2時間作業で5~7日かかっていました!
現在では3日程度で1記事を作ることができます(AIの実験する余裕もできました)
特に、構成案に沿った文章の下書きを作る時間が大幅に短縮されます。
空いた時間で、リサーチや記事構成に時間をかけることができるようになりました。
初心者でもできる?
AIライティングは初心者の方にこそおすすめです。
文章を書くのが苦手な人でも、AIがたたき台を作ってくれるので安心できます。
多くのツールは、直感的に操作できる分かりやすいデザインになっています。
何から書けばいいか分からない、という悩みを解決してくれます。
AIと一緒に文章を作ることで、ライティングスキルも自然と上達します。
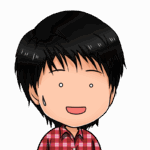
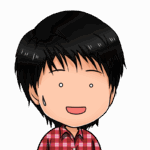
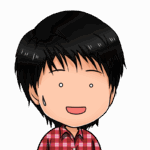
とはいえしっかりと自分でも学ぶ姿勢は大事ですよ!
AIが作った文章をしっかりと読み自分の言葉に変えましょう!
AIライティングのメリット


AIライティングには、たくさんのメリットがあります。
うまく活用すれば、ブログ運営がもっと楽しく、効率的になります。
ここでは、特に大きな3つのメリットを紹介します。
記事作成のスピードが劇的に向上する
最大のメリットは、記事作成のスピードが格段に上がることです。
これまで数時間かかっていた作業が、数十分に短縮されることもあります。
AIが文章の下書きを瞬時に生成してくれるおかげです。



僕の場合は5~7日以上かかっていた1万文字を超えるきじも3日ていどに短縮しました!
また、リサーチや構成作成の時間も短くなるため、全体の作業時間が減ります。
記事の更新頻度を上げたいブロガーにとって、非常に強力な武器になります。
ネタ切れの不安から解放される
AIは、ブログのネタ切れを防ぐのにも役立ちます。
一つのキーワードから、関連する様々なトピックや切り口を提案してくれます。
自分では思いつかなかったような、新しいアイデアが生まれることもあります。
読者がどんな疑問を持っているのか、AIに質問して記事のヒントを得ることも可能です。



僕の場合はとりあえずキーワード(ペルソナなど含む)と見出しで構成しを作り記事を書かせてから、ファクトチェックしています!
AIというアイデアの泉があれば、ネタ切れの心配はもうありません。
自分が知らないジャンルでも、AIに書いてもらってから調べることができるので「知らないから書けない」という問題も解決できます。
文章のクオリティを一定に保てる
AIを使えば、いつでも安定した品質の記事を作成できます。
人間のように、その日の体調や気分によって文章の質が左右されることがありません。
文法的な間違いや、誤字脱字が少ない文章を生成してくれます。
あらかじめ設定したルールに従って、一貫したトーンの文章を書くことも得意です。
ブログ全体の品質を高いレベルで保つのに、AIは大きく貢献します。



誤字脱字がないけど、記事の誤情報があるのでそこは注意が必要!
AIライティングのデメリット
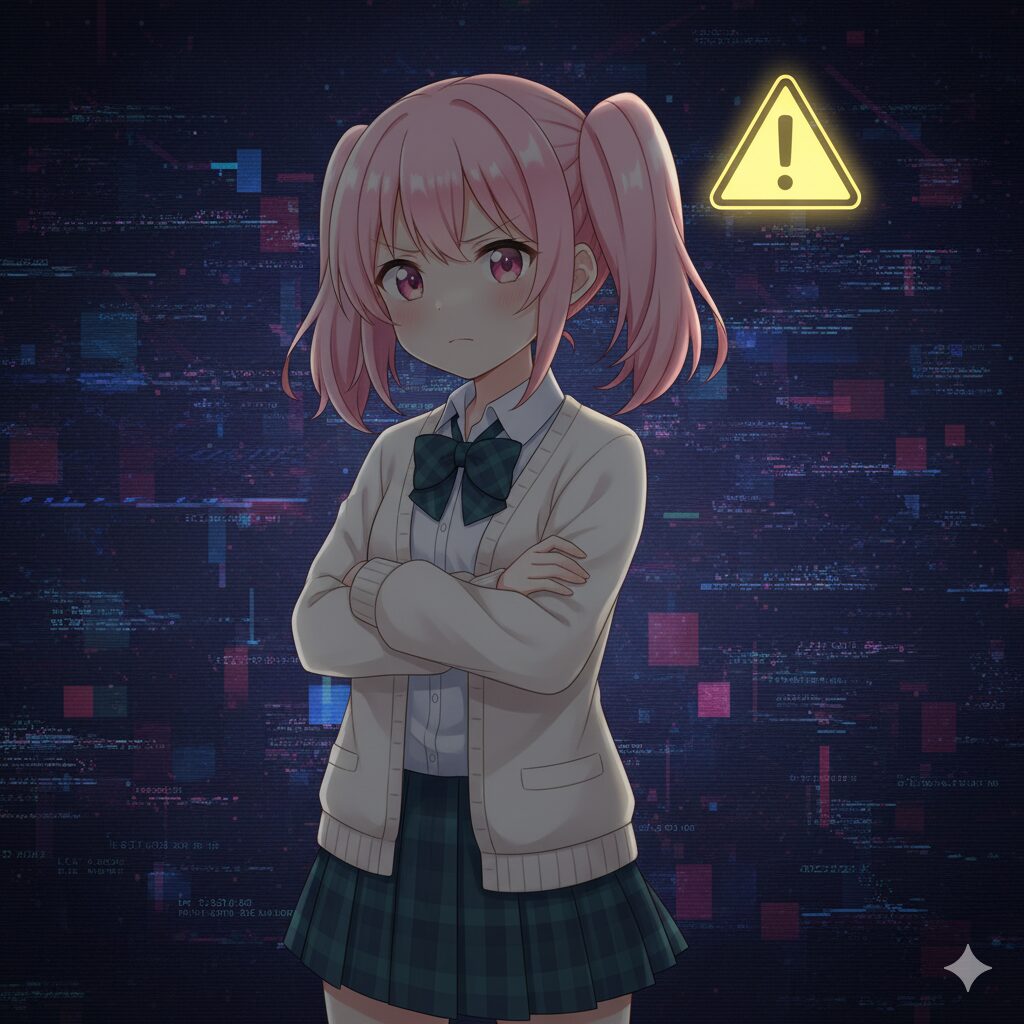
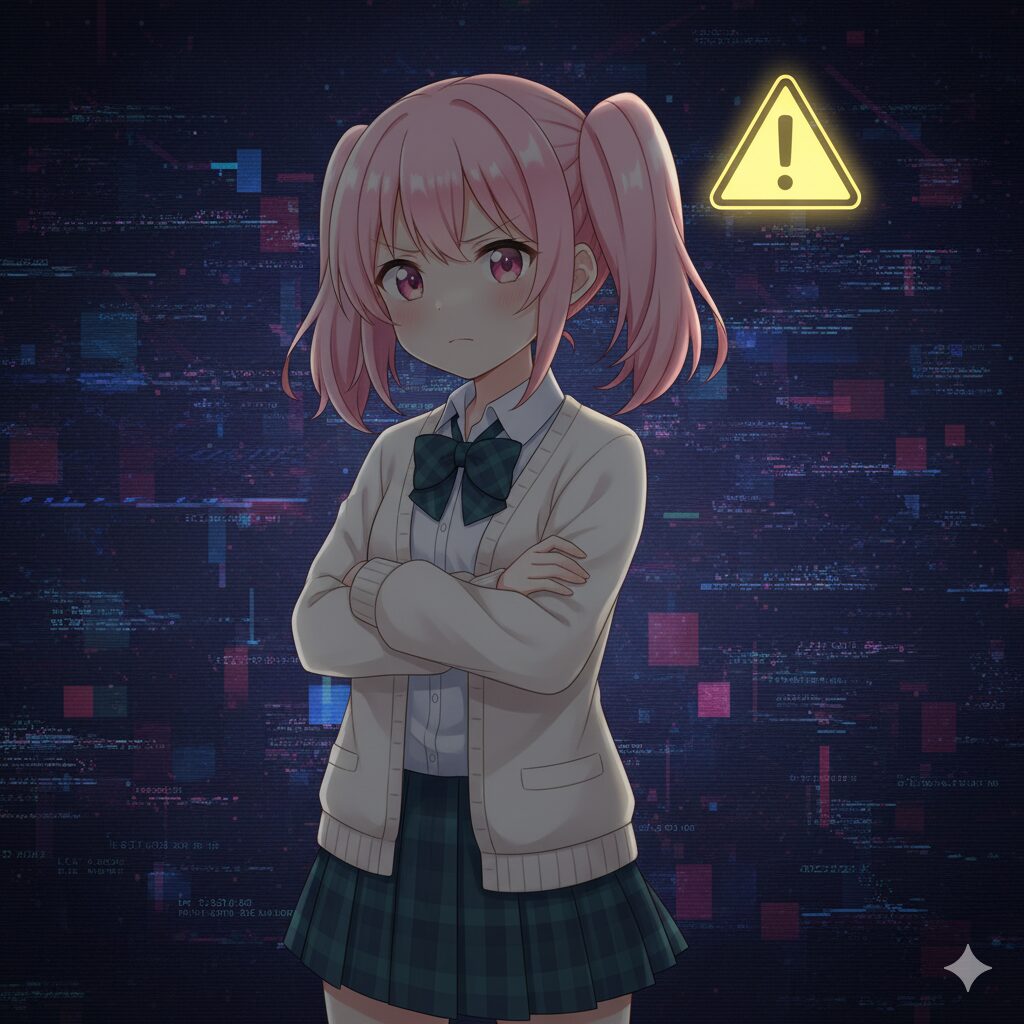
AIライティングは便利ですが、いくつかのデメリットも存在します。
注意点を知っておくことで、失敗を未然に防ぐことができます。
ここでは、AIライティングで注意すべき3つのデメリットを解説します。
情報の正確性に欠ける場合がある
AIが生成する情報が、常に正しいとは限りません。
古い情報や、事実とは異なる内容を、もっともらしく書いてしまうことがあります。
そのため、生成された文章は必ずファクトチェック(事実確認)が必要です。
特に、専門的な情報や最新のニュースを扱う際は、注意が求められます。
AIの情報をうのみにせず、信頼できる情報源で裏付けをとる習慣が大切です。



僕自身もブログではないけど、AIの情報を信じて行動しえらい目にあったことがあります!
オリジナリティや独自性が出しにくい
実はこれがAIの弱点ですプロンプトをどれだけしっかりと設定しても、個性を出すことは不可能です。
AIが書く文章は、どこか無機質で、個性に欠けることがあります。
インターネット上の情報を学習しているため、ありきたりな表現になりがちです。
読者の心を動かすような、ユニークな視点や体験談を盛り込むのが難しいのです。
AIが作った文章に、あなた自身の言葉や経験を加えることが不可欠です。
AI任せにせず、自分の色を出すことで、記事はもっと魅力的になります。
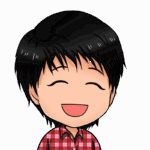
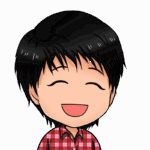
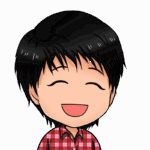
僕自身は最低でも必ず1記事に1か所は自分の文章で本文を書いたり、体験を書いたりしています!
使い方を誤るとSEO評価が下がる
AIで生成した文章を、そのまま公開するのは危険です。
低品質なコンテンツを大量に作ると、検索エンジンからの評価が下がる恐れがあります。
Googleは、読者の役に立つ、独自性の高いコンテンツを評価します。
AIはあくまで執筆を補助するツールとして使い、最終的には人の手で質を高めましょう。
読者のためになる記事作りを心がければ、SEO評価の低下は防げます。
ただし、高品質な記事を最初から作るのは不可能(効率が悪い)ので、AIが書いた記事+60%の記事を公開し、上位表示に近記事をリライトして上位表示を目指すのがおすすめです。



キーワード選定
ペルソナ設定
検索意図
見出し
をしっかりやれば、60%記事でも上位表示は狙えます!
AIライティングツールの選び方


AIライティングツールはたくさんあり、どれを選べばいいか迷いますよね。
自分に合ったツールを見つけることが、AIライティング成功のカギです。
ここでは、ツール選びで失敗しないための5つのチェックポイントを紹介します。
まずは「汎用AI」か「特化型ツール」か
ツールは大きく分けて、汎用AIと特化型ツールの2種類があります。
汎用AIで有名なのはChatGPTです。チャット方式で文章を作っていく感じですね。
汎用性ツールはなれれば一個で文章作成以外にも様々な用途で使えます。



僕がよく使っているのはGeminiとClaudです!
ただし、自由度が高いためプロンプト設定などをしっかりする必要があります。
一方、特化型ツールは、ブログ記事の作成など特定の目的に特化しています。
キーワードを入れるだけで、検索意図やペルソナ、見出しを設定し、中には画像まで生成するものもあります。
初心者は、テンプレートが豊富な特化型ツールから始めると使いやすいでしょう。
ただし、特化型ツールは文章に特徴が出しにくく書きたい内容と違う文章を生成されることも多くあります。
自分の目的やスキルに合わせて、どちらのタイプが合うか考えましょう。



僕の場合はいろいろ特化型ツールを使いましたが、うまくいかず今は汎用性ツールのGeminiやClaudを使っています!
機能性と生成される文章の質を確認する
ツールによって、搭載されている機能や文章の品質は様々です。
SEOに強い文章が作れる機能や、コピペチェック機能があると便利です。日本語のうまい下手もあります。
実際に生成された文章のサンプルを見て、その質を確認しましょう。
口コミやレビューサイトで、他のユーザーの評価を参考にするのも良い方法です。
自分が求める機能がそろっていて、納得できる品質のツールを選びましょう。
無料体験が設定されているものも多いので、試してみるのもいいですよ。
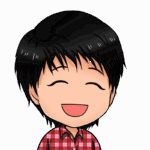
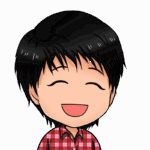
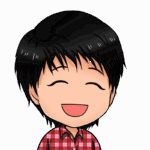
試すのが一番ですからね!
僕の場合は無料で試したり、一番下のプランで体験し手から決めています!
料金プランとセキュリティ体制を比較する
料金プランは、自分の利用頻度や予算に合ったものを選びましょう。
毎月決まった額を払うプランや、使った分だけ払うプランなどがあります。
無料で使える範囲が広いツールもあるので、まずはそこから試すのも手です。
また、入力した情報がどう扱われるか、セキュリティ体制も確認しておくと安心です。
長く使い続けるためには、料金と安全性の両方をしっかり比較することが大切です。
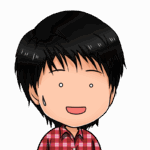
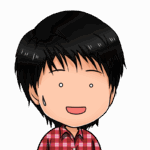
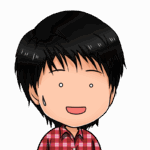
僕の場合毎月決まった料金を払う定額プランにしています!
めちゃAI使うので使った分は怖すぎる…
日本語に違和感がないかチェックする
海外製のツールの場合、日本語が不自然なことがあるので注意が必要です。
翻訳したような、かたい表現や不自然な言い回しが使われることがあります。
生成された文章を読んでみて、自然で読みやすい日本語になっているかを確認します。
日本製ツールや、日本語に最適化されたツールを選ぶと失敗が少ないです。
自然な日本語で書けるツールは、修正の手間が省けるのでおすすめです。



これも実際に使ってみないとわかりません!
「日本語がうまい」と書いてあっても違和感があるAIは結構多かったりします!
無料トライアルで相性を試してみる
多くのツールには、無料トライアル期間や無料プランが用意されています。
実際に自分で使ってみて、操作のしやすさや文章の質を確かめるのが一番です。
いくつかのツールを試してみて、自分との相性が最も良いものを選びましょう。
使ってみないと分からないことはたくさんあります。
気になるツールがあれば、まずは気軽に無料トライアルを申し込んでみてください。



試すのが一番手っ取り早いですからね!
代表的なAIライティングツール5選


ここでは、僕が実際に使ってみておすすめできるAIライティングツールを紹介します。
それぞれに特徴があるので、あなたの目的に合ったツールを見つけてください。
汎用AIとブログ作成に特化したツール、合わせて5つをピックアップしました。
- 代表的な汎用AI(Claude・ChatGPT・Gemini)
- ラクリン:たった数分でブログ記事が完成
- Catchy:キャッチーな見出しや文章を生成
- Notion AI:メモからシームレスに記事作成
- Transcope:SEOに強い文章を生成するなら
代表的な汎用AI(Claude・ChatGPT・Gemini)
汎用AIは、アイデア出しから文章作成まで幅広く活躍します。
無料で始められるものが多く、AIライティング入門に最適です。
特にClaudeは、自然な日本語の生成能力が高いと評判です。
ChatGPTは最も有名で、情報量も多く、様々な用途に活用できます。
GeminiはGoogle製で、最新情報や検索との連携に強いのが特徴です。
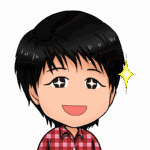
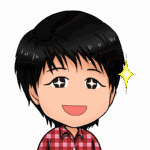
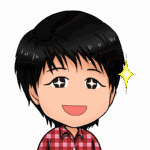
僕の場合はClaudとGeminiを主に使っています!
ChatGPTは少し苦手です!



結局、汎用性AI(Claude・ChatGPT・Gemini)はどれがいいの?
と思っている人もいるでしょう。こちらの記事にに実際に比較した結果や使い方などを書きましたので是非読んでください。
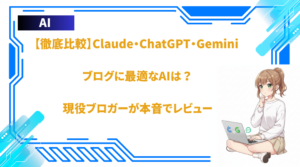
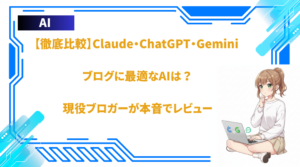
ラクリン:たった数分でブログ記事が完成
ラクリンは、ブログ記事の作成に特化した国産ツールです。
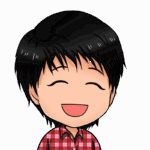
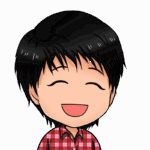
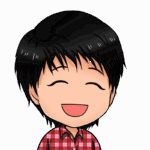
しかもブログ・アフィリエイトでサロンをやったりしているマクリンさんが開発したツールです!
専門でやっている方が作ったので、信頼度は高いです!
キーワードを入力するだけで、構成案から本文までを自動で作成してくれます。
操作がとてもシンプルで、初心者でも迷うことなく使えるのが魅力です。
記事作成の時間をとにかく短縮したい、という人に向いています。
まさに名前の通り、楽にライティング作業ができる心強い味方です。
Catchy:キャッチーな見出しや文章を生成
Catchyは、魅力的な広告文や見出しを作るのが得意なツールです。
ブログ記事だけでなく、SNSの投稿文やメルマガ作成にも役立ちます。
100種類以上の生成ツールが用意されており、様々な場面で活用できます。
読者の心をつかむ、キャッチーな表現を生み出したいときに重宝します。
文章のアイデア出しや、部分的な文章作成のサポート役として優れています。
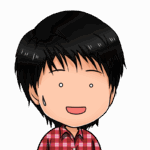
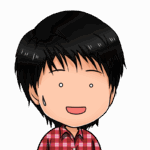
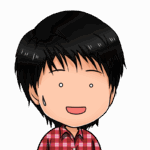
まあ僕が使ったのは2年ほど前ですが、やれることが多すぎてテンプレートに迷うのが弱点です!
とはいえ国産で多分日本語も進化し、やれることも多いので一度試すのはどうでしょう!
Notion AI:メモからシームレスに記事作成
Notion AIは、人気のメモアプリNotionに搭載されたAI機能です。
普段からNotionで情報管理をしている人には、特におすすめです。
メモ書きやアイデアの断片から、AIが文章を生成・要約してくれます。
別のツールを立ち上げることなく、Notion内で作業が完結するのが便利です。
情報整理から記事執筆までを、スムーズにつなげることができます。



僕の弟がススメていたツール!
僕の場合はAIが出力した文章をWordpressに貼り付けるので結局使いませんでしたが…
いったんメモ書きする人にとってはおすすめです!
Transcope:SEOに強い文章を生成するなら
Transcopeは、SEOに特化したAIライティングツールです。
検索上位の記事を分析し、SEOに有利な構成案や文章を作成してくれます。
競合サイトにどんな情報が含まれているかを、簡単に把握することができます。
キーワードや共起語を適切に含んだ、質の高い文章が生成できるのが強みです。
本気で検索上位を目指したいブロガーにとって、頼れるツールとなるでしょう。
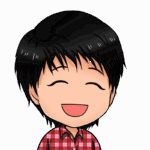
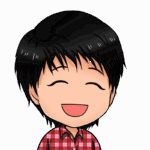
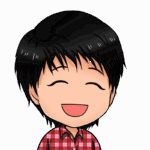
コピーコンテンツ調査、リライト、文章校正など機能が豊富です!
ただ、料金が高いのがデメリットですね…
興味のある方は無料体験から使ってみましょう!
文字数指定もOK!AIへの指示文(プロンプト)のコツ
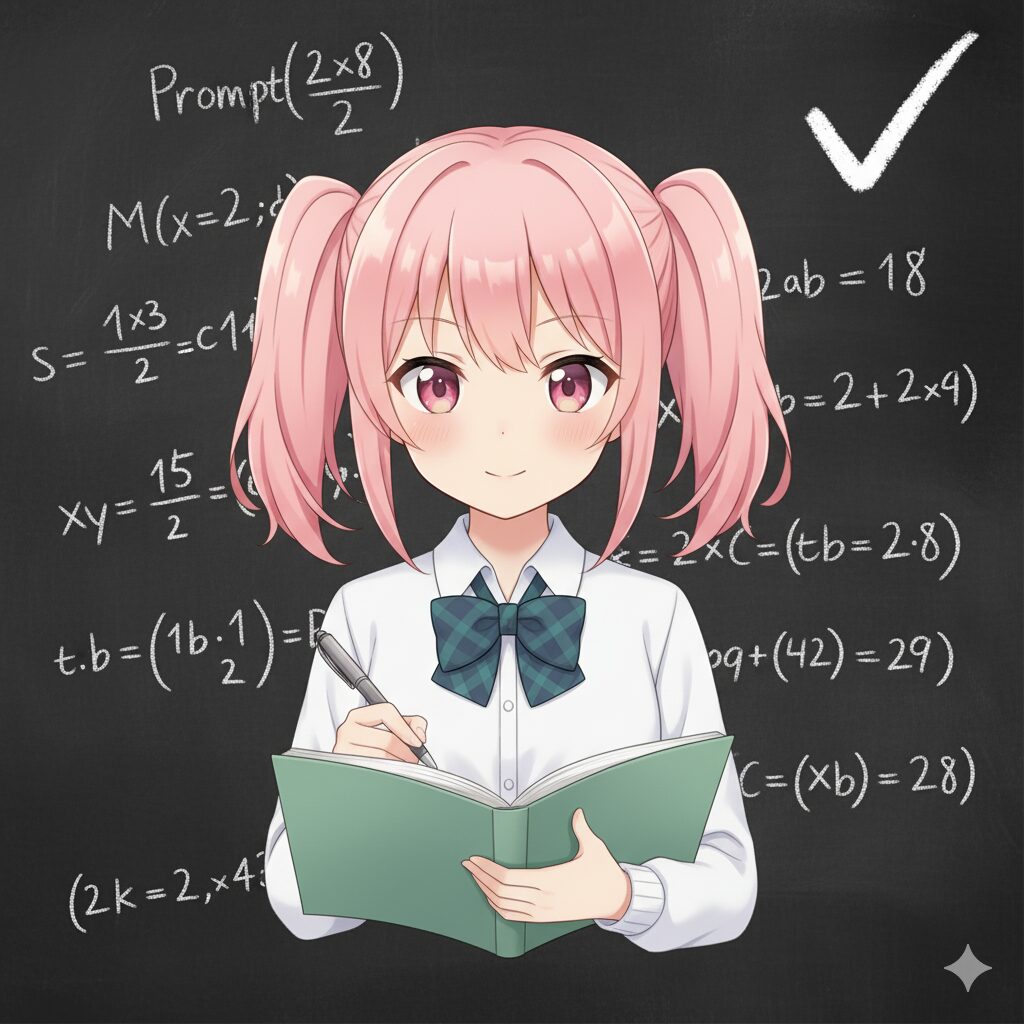
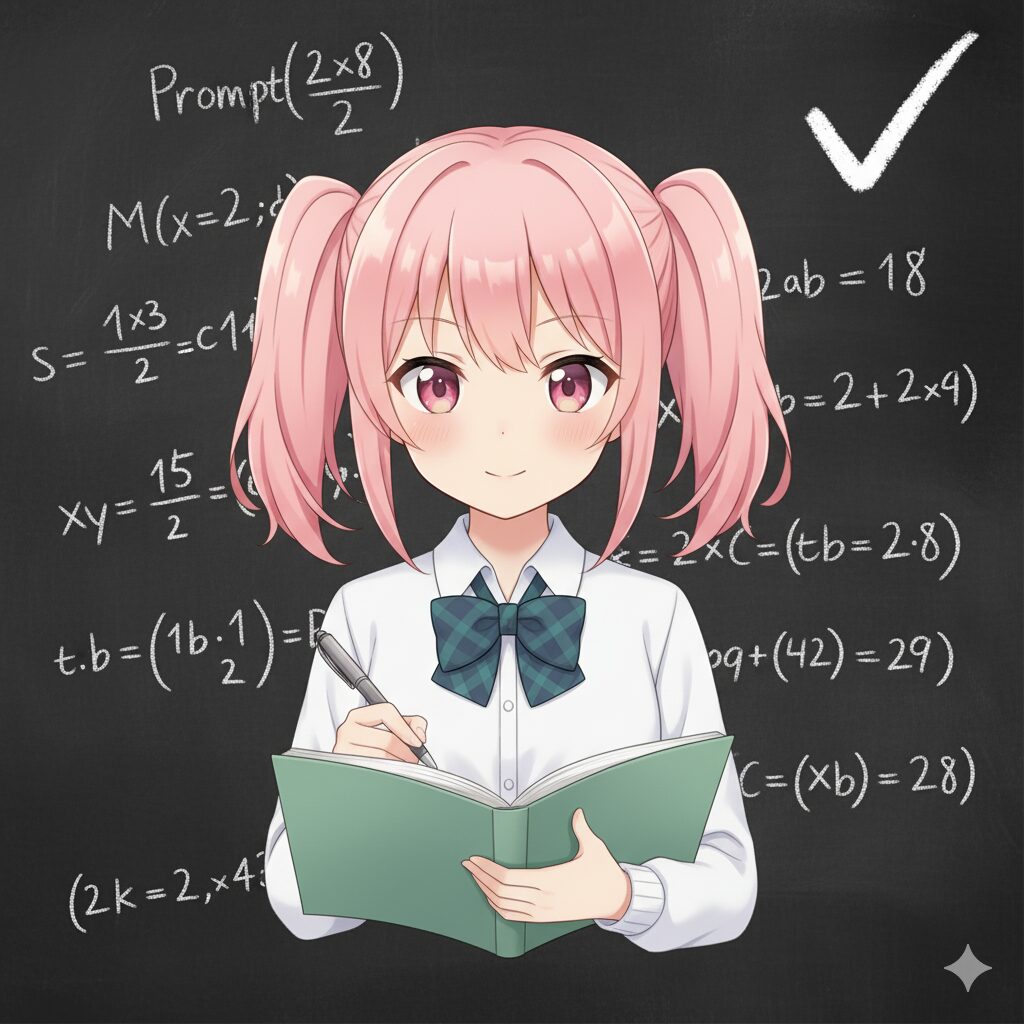
AIから質の高い文章を引き出すには、指示文(プロンプト)が重要です。
AIを上手に操るための、プロンプト作成のコツを解説します。
これから紹介する4つのポイントを意識すれば、AIの性能を最大限に引き出せます。
基本構成は「役割・目的・条件」
優れたプロンプトは、「役割」「目的」「条件」の3要素で構成されます。
まず、AIに「プロのブロガー」のような役割を与えます。
次に、「ブログ記事を書いて」という目的を明確に伝えます。
最後に、文字数や文体、含めてほしいキーワードなどの条件を指定します。
この型を意識するだけで、AIの回答の精度は大きく向上します。



AIに指示を出す方法を変えるだけで精度が段違いに上がります!
効果的な文字数指定のテクニック
文字数を指定する際は、あいまいな表現を避けるのがコツです。
「短めに」ではなく、「200字程度で」のように具体的な数字で指示します。
ただし、AIは正確な文字数制御が苦手なこともあります。
「〇〇字〜〇〇字の間で」のように、幅を持たせて指示するのも有効な方法です。
何度か試してみて、使っているAIのクセをつかむことも大切です。
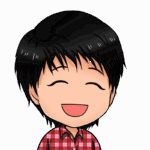
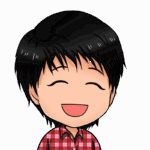
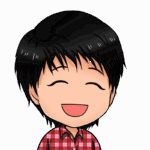
「〇〇字〜〇〇字の間で」と指示出しても、少し少なくなりがちなので…
僕の場合は誤差を計算し、+100文字くらいで設定しています!
ペルソナ設定で文章の質を高める
誰に届けたい文章なのか、ペルソナをAIに伝えることで質が高まります。
「20代のブログ初心者の男性」のように、読者の人物像を具体的に設定します。
ペルソナの年齢や興味、悩みを伝えることで、より読者に寄り添った文章が生まれます。
AIは、そのペルソナに響く言葉遣いや表現を選んでくれるようになります。
文章のトーンを統一するためにも、ペルソナ設定は非常に効果的です。
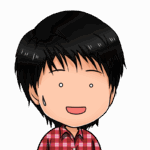
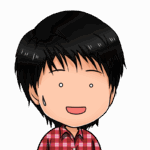
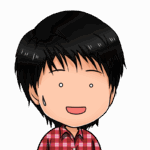
個人向けで書いているつもりが読んでみたら企業向けになっていることもあります!
参考記事を与えて精度を上げる方法
文章のトーンや構成の参考になる記事を、AIに読ませるのも良い方法です。
「この記事のような雰囲気で書いて」とURLを提示して指示します。
AIは参考記事のスタイルを学習し、似たテイストの文章を生成してくれます。
自分のブログの過去記事を参考にさせることで、サイト全体の統一感を保てます。
手本を示すことで、AIはあなたの意図をより正確に理解してくれます。



僕の場合は自分の過去に書いた記事を読ませて例文を作ってプロンプトに組み込みました!
例文や参考記事があるのでは記事の質が劇的に変わります!
AIで記事を書いても大丈夫?


最後に、多くの方が不安に思っている「AIで記事を書いても大丈夫なのか?」という疑問にお答えします。
結論から言うと、正しい使い方をすれば、AIはブログ運営の強力な味方になります。
この章では、AIと上手に付き合っていくための4つの大切な心構えをお伝えしますね。
AI記事の品質とSEO効果の真実
結論としてAIを「パートナー」として活用すれば、SEOに効果的な高品質な記事を作成できます。
Googleの公式見解でもAIが作ったからという理由だけで、ペナルティを受けることはないとされています。
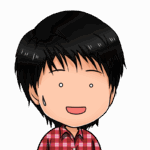
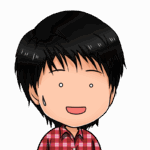
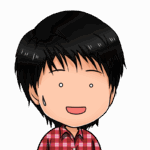
そもそもGoogleからGeminiを出しているんだから、ペナルティは受けないでしょ(笑)
大切なのは、内容が薄っぺらな「低品質コンテンツ」にならないようにすることです。
僕自身AIを活用することで、記事の文字数が1万字を超え、執筆時間も半分以下になりました。
AIだけに頼り切るのではなく、最終的に人間が品質を管理すれば何も心配することはありません。



AIだけで記事を量産で確かに上位表示は可能です(実際に僕のもう一つの実験用ブログではしています)
ただし、キーワード選定やプロンプト設定など結構大変です!
一番いいのはAIで作った文章に、自分の1次情報を付け足すことですね!
読者満足度への影響は?
読者にとって大切なのはAIが書いたかどうかではなく、自分の悩みが解決したかどうかです。
AIが作った記事でも情報が正確で、構成が論理的であれば読者満足度は高くなります。
逆に人間が書いても、誤った情報や読者に寄り添わない文章では満足度は低くなります。
AIが書いた文章に、あなた自身の体験談や感想を加えることでさらに満足度は高まります。
重要なのは、常に読者の問題を解決することを第一に考える姿勢です。



AIが書いた情報は誰かの文章の書きなおしにすぎません!
それでもいいのですが、しっかりと自分で見直し考えながら自分の感想などを入れることも重要です!
AI活用時の注意点と対策法
AI活用で失敗しないために、絶対に守ってほしい3つの注意点があります。
僕の失敗談も参考にして、あなたには同じ過ちを繰り返してほしくありません。
- ファクトチェックを必ず行う
- 自分の言葉でリライトする
- 独自の体験談や感想を追加する
- コピペチェックは必ずする
AIは時々自信満々に嘘をつくことがあるので、情報の裏付けは必須です。
また、AIが生成した文章をそのまま公開するのは絶対にやめましょう。たまにコピペチェックしていたらレッドゾーンになっていることもあります。
「簡単に儲かる」といった甘い言葉に惑わされず、地道な努力を続けることが成功への近道です。
人間ライターとの併用がベストな理由
結論として、AIは人間の仕事を「奪う」のではなく、あくまで「効率化するツール」です。
人間とAIが協力し、それぞれの得意なことを分業するのが、現時点で最も良い方法です。
AIに記事の下書きや構成案作成を任せ、人間は最終的な品質管理や独自性の追加に集中します。
この方法で、僕の執筆時間は1週間から2〜3日へと、劇的に短縮されました。
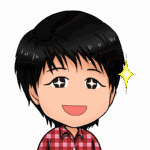
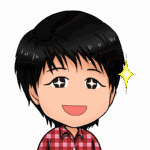
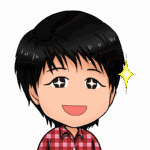
AIはライバルではなく、僕のビジネスパートナーでありカウンセラーのような存在です!
AIでできる仕事は任せて、自分でしか出いないことに集中しましょう!
【まとめ】AIライティングのやり方!現役ブロガーの僕がやっている文章作成方法
今回の記事では、現役ブロガーが実践するaiライティングのやり方と、効率的なai文章作成のコツを解説しました。
- 5ステップでAI記事を量産する
- 目的別に最適なAIツールを選ぶ
- プロンプトのコツで精度を上げる
- ファクトチェックで独自性を加える
- AIと人間の協業で収益化を目指す
この記事で紹介した5つのステップを実践すれば、誰でも簡単に質の高い記事を作成できます。大切なのは、あなたの目的に合ったAIライティングツールを選ぶことです。
さらに、効果的なプロンプトのコツを掴み、人間によるファクトチェックとリライトを加えれば、AIが書いたとは思えないほど自然で価値のある文章が完成するでしょう。
さあ、AIライティングのやり方をマスターして、あなたのブログ運営を加速させませんか?